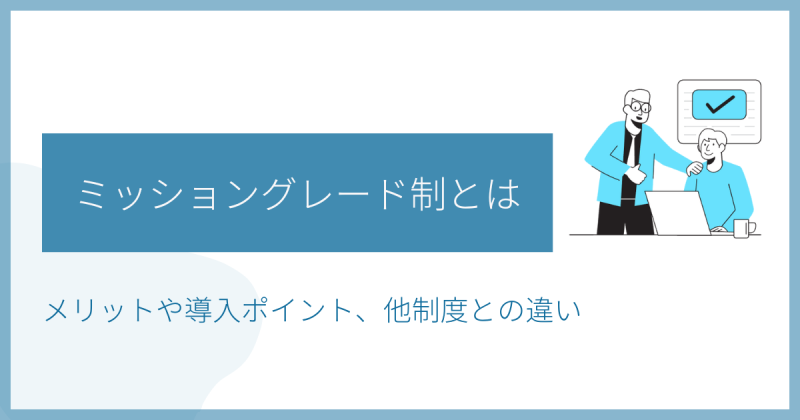
働き方改革や多様な人材活用が求められる現代の企業において、従来の年功序列型評価ではなく「成果」を重視する人事制度への移行が進んでいます。その中でも注目を集めるのが「ミッショングレード制度」です。時間や場所にとらわれず、「何を達成したか」を評価軸とするこの制度は、テレワークの普及や多様な働き方を推進する企業にとって理想的な人事評価の仕組みといえるでしょう。
本記事では、ミッショングレード制度の基本概念から導入メリット、他の人事制度との違い、そして現場への定着方法まで、わかりやすく解説します。
ミッショングレード制度とは、社員の評価を「何を達成したか」に基づいて行う人事評価制度です。従来の年功序列や勤務時間を重視する制度とは異なり、個人やチームに与えられた「ミッション(使命・任務)」の達成度によって評価されます。
具体的には、各社員に明確なミッションと目標(KPI)が設定され、その達成度や貢献度に応じて等級や報酬が決定されます。等級は通常、ミッションの難易度や責任の重さによって複数のグレードに分けられており、成果に応じてグレードアップしていく仕組みとなっています。
この制度の最大の特徴は、「いつ」「どこで」「どのように」働くかは問わず、「何を」「どれだけ」成し遂げたかを重視する点にあります。そのため、時間や場所に縛られない柔軟な働き方と親和性が高く、多様な働き方を推進する企業で導入が進んでいます。
ミッショングレード制度は、多様な人材に対応できます。
「いつ」「どこで」働くかではなく「何を」達成したかを評価するという原則が、多様性を受け入れる土台となります。育児・介護と仕事の両立、地方や海外からのリモートワーク、副業との並行など、従来の「同じ時間・同じ場所」の働き方では難しかった多様な働き方を可能にします。
具体的には、在宅勤務やサテライトオフィス勤務などのテレワーク、コアタイムなしのフレックスタイム制、週3〜4日勤務などの時短勤務といった柔軟な働き方と組み合わせることで、ライフステージの変化に左右されない継続的なキャリア形成を支援します。正社員以外にも、プロジェクト単位での業務委託や副業人材など多様な雇用形態の人材を、同じ「ミッション達成」という基準で公平に評価・活用できるため、多様性のある組織づくりが可能になります。
これにより、育児・介護中の社員の離職防止、障がいのある人材や地方在住者の活用、シニア層の経験・知見の活用など、従来見過ごされがちだった多様な人材の強みを組織の成長に結びつけることができます。
ミッショングレード制度の導入により、組織全体の生産性向上が期待できます。
成果主義の考え方により、本質的でない業務が自然と削減されます。従業員は与えられたミッションを効率的に達成するための最適な方法を自ら考えるようになり、業務の無駄が排除されていきます。
また、明確な目標設定とその達成による適正な評価・報酬が約束されることで、従業員のモチベーションが向上します。目標達成の喜びと評価の納得感がモチベーションを高め、自発的な業務改善や創意工夫が生まれやすくなります。
若手でも高い成果を出せば正当に評価される環境が整い、多様な人材の意欲と能力を引き出すことができます。
ミッショングレード制度の重要なメリットの一つが、客観的で公平な評価基準の確立です。人事評価が、明確な成果指標に基づく客観的なものへと変わります。
「何をどこまで達成すれば評価されるのか」が数値目標や具体的な成果物として明示されるため、評価の透明性が高まります。社員にとっては評価基準が明確になることで「頑張れば正当に評価される」という信頼感が生まれ、上司にとっては感情や印象に左右されない公正な評価が可能になります。
さらに、組織全体で一貫した評価基準を適用することで、部署や上司による評価のバラつきを抑制し、評価者バイアスの影響を最小化できます。ミッションという明確な基準があることで、上司だけでなく同僚や部下、さらには顧客など様々な視点からの多面的評価も導入しやすくなり、より立体的で正確な人材評価システムを構築することが可能になります。
ミッショングレード制度を導入する上での課題の一つが、評価基準の曖昧さです。「成果」を軸とした評価を行うことは理想的ですが、その成果をどう定義し、どう測定するかという点が課題となります。
特に、定量化しにくい業務や長期的な取り組みが必要な業務では、適切な評価指標の設定が難しくなります。例えば、営業職なら売上という明確な数値がありますが、企画職や研究開発職などでは成果の測定が容易ではありません。
また、部署や職種によって成果の質や規模が異なるため、横断的に公平な評価基準を設定することも困難です。同じ「A評価」でも部署によって達成難易度に差があると、社員の不満や不公平感につながります。
成果主義とリモートワークなどの柔軟な働き方を組み合わせたミッショングレード制度では、数字に表れない貢献(チームへの協力、社内の雰囲気づくり、知識共有など)が評価されにくいため、従業員間のコミュニケーションが希薄化するリスクがあります。
各自が自分のミッション達成に集中するあまり、チームとしての連携や部門を超えた協力が減少する傾向が見られます。特に在宅勤務やリモートワークが増えると、偶発的な対話や雑談から生まれるアイデアや情報共有の機会が失われがちです。
組織の一体感やチームワーク、企業文化の維持も課題となります。同じ時間・同じ場所で働くことで自然と醸成されていた組織文化や帰属意識が薄れてしまうリスクがあります。
ミッショングレード制度を効果的に運用するためには、相応の時間とコストがかかります。
まず、個々の社員に合わせた適切なミッションの設定が必要です。単なる業務の割り当てではなく、個人の能力・経験と組織目標を結びつけた意味のあるミッションを設計するには、管理職の高いスキルと時間が求められます。
また、定期的な進捗確認や成果測定、フィードバックのプロセスも負担となります。特に多面評価など複雑な評価方法を導入する場合、評価データの収集・分析・フィードバックまでの一連の流れが管理職の大きな業務負担となります。
職能資格制度は、個人の「能力」に着目し、保有するスキルや知識によって等級を決定する制度です。一方、ミッショングレード制度は「成果」に着目し、実際に達成した結果で評価します。
| 比較項目 | 職能資格制度 | ミッショングレード制度 |
|---|---|---|
| 評価の焦点 | 「能力」(保有するスキルや知識) | 「成果」(実際に達成した結果) |
| 昇格・昇給の基準 | 能力の向上、資格の取得、勤続年数 | ミッションの達成度、組織への貢献度 |
| 年功要素 | 年功的な評価が温存されやすい | 年齢に関係なく成果で評価 |
| 若手の評価 | 経験やスキル不足により評価に限界がある | 成果を出せば若手でも高評価が可能 |
| 評価の客観性 | 能力の判断に主観が入りやすい | 成果という客観的指標で評価しやすい |
職務等級制度は、「職務(ジョブ)」に着目し、職務の難易度や責任の重さによって等級を決定する制度です。ミッショングレード制度は職務よりも個別の「ミッション」に焦点を当てています。
| 比較項目 | 職務等級制度(ジョブグレード) | ミッショングレード制度 |
|---|---|---|
| 評価の焦点 | 「職務」(ジョブ)の価値や重要度 | 「ミッション」の達成度 |
| 等級の決定要素 | 職務の難易度、責任の大きさ、市場価値 | ミッションの難易度と達成状況 |
| 職務範囲 | 明確に定義された職務範囲(ジョブディスクリプション) | 目標達成のためなら職務範囲を超えた行動も評価 |
| 人材活用の特徴 | スペシャリスト育成に適している | ゼネラリストとスペシャリスト両方に対応可能 |

引用:Sansan株式会社
Sansan株式会社(サンサン)は、2007年に設立された日本のIT企業で、法人向けクラウド名刺管理サービス「Sansan」や個人向け名刺アプリ「Eight」などを提供しています。
ミッショングレード制度を導入し、マネジメントラインとプロフェッショナルラインに分かれたキャリアパスを整備。年2回の人事評価では、上司だけでなく、他部署や同僚の声も取り入れて評価する仕組みを採用しています。
グレードが上がるほど、期待される役割や責任の範囲も広がります。
参考:Sansan社内制度責任者が質問に答えます。「全ての社員が活躍できる」環境をつくるために

引用:株式会社リクルート
株式会社リクルートは、総合人材サービス企業であり、リクルートホールディングスの中核を担う事業会社です。「まだ、ここにない、出会い。」を企業理念に掲げ、個人と企業をつなぐ多様なマッチングサービスを展開しています。
株式会社リクルートのキャリア採用ではミッショングレード制度が採用されています。個人に対して上長や各組織の人材開発委員会が職務遂行能力を見立て、期待値を設定し、それに見合う職務とマッチングさせます。
そして担当することになった職務の価値をミッショングレードとして設定しています。
ミッショングレード制度の導入を成功させるためには、まず明確な方針決定が不可欠です。この段階では、経営層と人事部門が中心となり、以下のポイントを検討します。
方針決定の段階では、経営トップのコミットメントを確保することが成功の鍵となります。トップが制度の意義や目的を理解し、積極的に推進する姿勢を示すことで、組織全体の受容度が高まります。
役割定義書は単なる文書ではなく、制度運用の基盤となるものです。現場管理職や一部の社員を交えたワークショップ形式で作成することで、実態に即した内容になり、後の受容度も高まります。また、定期的な見直しを前提とした柔軟性のある設計にすることも重要です。
新しい制度の導入には、社員の理解と納得が不可欠です。社内周知は単なる情報伝達ではなく、制度への信頼と期待を醸成するプロセスです。
周知の際は、「制度を押し付ける」のではなく「一緒によりよい組織をつくる」という姿勢が重要です。特に中間管理職は制度を実際に運用する立場にあるため、彼らの理解と協力を得ることが成功の鍵となります。また、周知は一度で終わりではなく、運用開始後も定期的な再周知や理解度確認を行うことが効果的です。
マネジメント層の間で評価の基準や捉え方がバラバラだと、どんなに制度設計が整っていても、不公平感や不信感を招きます。
ミッションや評価基準の意図を正しく共有し、共通の評価軸を持ってもらうためには、制度導入前後での評価者研修や評価会議の設計が不可欠です。
評価者研修では、制度の理念や目的の理解だけでなく、実践的なスキルトレーニングが重要です。具体的な事例を用いた評価演習や、ロールプレイングを通じたフィードバック練習などを通じて、評価基準の解釈を一致させます。また、部門間での評価基準の調整(キャリブレーション)会議を定期的に実施し、組織全体での評価の公平性を担保することも大切です。
被評価者である社員が、制度の目的や評価基準を正しく理解していなければ、「何を評価されているのかわからない」という不信感に繋がります。
導入時の説明だけでなく、定期的な社内説明会や個別フィードバックを通じて、制度が単なる仕組みではなく、「企業からの約束」として浸透するよう工夫することが大切です。
社員向け説明では、制度の運用方法だけでなく、「なぜこの制度を導入するのか」という背景や目的を丁寧に説明することが重要です。多様な働き方を実現し、一人ひとりの強みを活かした組織づくりという本来の目的を繰り返し伝えることで、単なる評価制度ではなく「成長と活躍のための仕組み」という認識を醸成できます。
どんなに綿密に設計したミッショングレード制度も、実際の運用の中で課題が明らかになります。固定的な仕組みではなく、進化し続ける制度として捉えることが重要です。
定期的なアンケート調査や意見交換会を通じて、制度の効果や課題点の把握を行います。特に、「制度の目的が達成されているか」「運用上の不便や不公平はないか」「想定外の副作用は生じていないか」といった点を継続的に検証することが大切です。
収集したフィードバックを基に、短期的な運用改善と中長期的な制度改定を計画的に進めていきます。改善のプロセスは透明性を持って進め、変更の背景や目的を丁寧に説明することで、制度への信頼感を維持します。最初から完璧を目指すのではなく、小さな改善を積み重ねながら、組織の成長と共に制度も成熟させていく姿勢が大切です。
ミッショングレード制度は、「何を達成したか」という成果に基づいて評価を行う人事制度であり、多様な働き方を支援する現代の組織に適した評価の仕組みです。職能資格制度や職務等級制度と比較して、成果と貢献に焦点を当てることで、年齢や勤続年数に関わらず公平な評価が可能となります。
この制度の導入により、多様な人材の活用、生産性の向上、客観的な評価基準の確立といったメリットが期待できます。一方で、評価基準の曖昧さ、コミュニケーションの希薄化、制度運用の負担といった課題も存在します。
導入にあたっては、明確な方針決定、詳細な役割定義書の作成、丁寧な社内周知が重要です。また運用段階では、評価者研修による判断基準の統一、社員への制度意義の浸透、継続的な制度の見直しが成功の鍵となります。
導入事例として挙げたSansanやリクルートのように、自社の状況に合わせた制度設計と運用を行うことで、組織全体の成長と個人の活躍を両立させる環境を構築することができるでしょう。多様性と成果を両立させる組織づくりを目指すなら、ミッショングレード制度の導入を検討する価値があります。
| Q1.ミッショングレード制度のメリットは |
|---|
|
以下のようなメリットがあります。
詳しくは、「ミッショングレード制度のメリット」をご覧ください |
| Q2.導入方法を教えて下さい。 |
|
以下のステップで導入できます。
詳しくは、「ミッショングレード制度の導入方法|検討から運用開始までのステップ」をご覧ください。 |